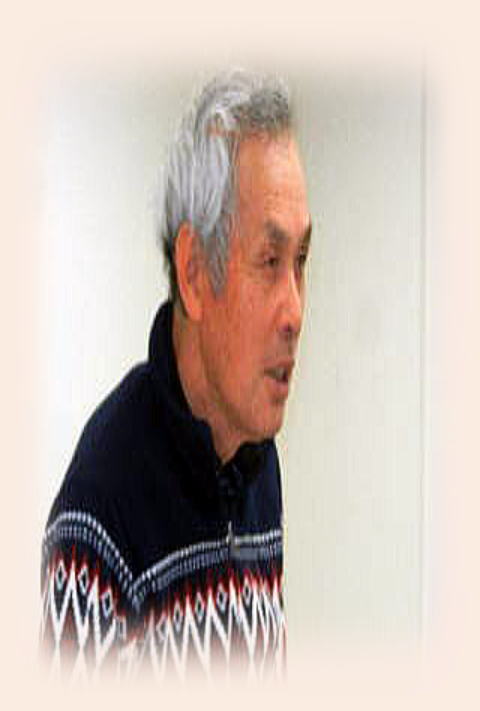
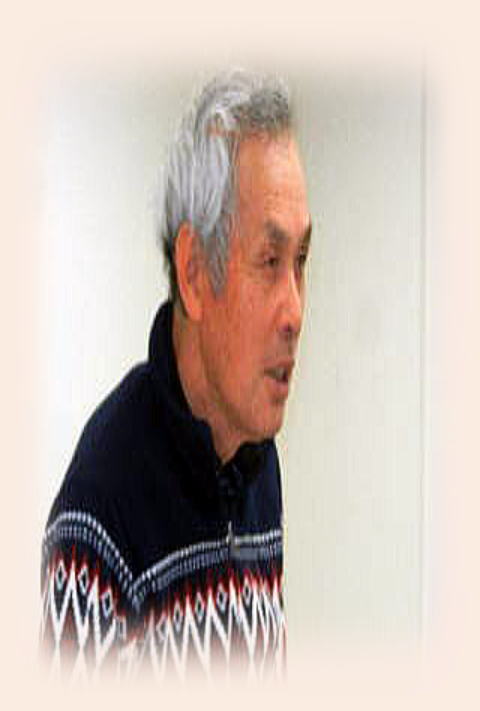
県央史談会
会長 内藤桂康
県央史談会の歴史
厚木市域には、県央史談会創立の前から、郷土の歴史に興味をもつ人は少なくはなかったようです。
石器、土器を拾い集めて研究したり、学校の先生方が集まって研究会を作ったりもしてきました。
そのような中、日本民俗学の祖・柳田國男が津久井郡内郷村で日本初の村落調査を行ったことで刺激を受けた人たちや、後に柳田の指導を受けて研究者として名前を残した人もありました。
県央の郷土史家にはこの人々の影響を受け、それぞれの地域の人が、互いに誘い合ってグループに参加しあった時期もあったようです。
学校の先生方が中心だった「北相文化研究会」が活動を休止したところで
鈴村茂さんはじめ市民の郷土史愛好家が合流して誕生したのが、「県央史談会」(=写真)です。
厚木史談会ではなく、「県央」としたところに以前のグループとは違いがありました。
しかし、自分たちが暮している土地のことを知りたくて、調べ、記したという点は変わりがありません。
そこには、深い愛情が感じられます。資料館施設の大事なミッションの一つは「郷土愛の涵養かんよう」ともいわれています。
涵養とは、水がしみ込むように徐々に養い育てること。つまり、市民の方々に郷土に関する知見を提供し、郷土に対する愛を育む、資料館の大切な仕事でもあります。
県央史談会は昭和35年9月に発足。厚木を中心とした県央地域の歴史研究家が主な会員となり始まった。
主な活動は機関誌『県央史談』の発行、史跡めぐり、文化財調査。発足当時は荻野の絵師・歌川国経の作品発見や、古沢で土器の発掘調査会を行うなど、精力的に調査活動を行ってきた。
厚木市郷土資料館NEWS1542011年12月より抜粋
